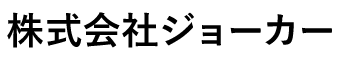みなさんこんにちはジョーカーの中村です。
三重県の作業場も終わりが近づいて来ました。
留まであと1週間、来年から千葉県に行くので途中で抜けて申し訳ないございません。
年内限りですが、出来る限り全力で頑張ります。
それでは
日本建築学会 建築工事標準仕様書(JASS5)によれば、屋根スラブ下場筋の定着長さは、特記のない場合、5d以上とする。
ふりがな
にほんけんちくがっかい けんちくこうじひょうじゅんしようしょ(JASS5)によれば、やねスラブしたばきんのていちゃくながさは、とっきのないばあい、5dいじょうとする。
?屋根スラブ下場筋…?一般階のスラブ下場筋と違うの?…インターネットの画像表記で見ると下場筋は10d以上150㎜以上と書いてあるけれど…変わったのかもしれません…?ん?ん?なんだ?
L2h?L3h?なんだその記号!
L1.L2.L3じゃないの?!20年〜30年前は無かったと思う…調べてみると…
建築ノート.コムのJASS5によると
コピーして貼り付けてしまいました。
小梁・スラブ上端筋の梁への90°折曲げ定着の場合
次に、小梁・スラブ上端筋が下図左で90°折曲げ定着L2hを確保できない場合は、
上記右La(投影定着長さ)の規定がLbに置き換わることと、
小梁の下端筋の定着長さL3h
の規定が適用されます。
90°折曲げ定着で定着長さL2hが仕口で確保できない場合の条件をまとめると以下のようになります。
- 定着起点から鉄筋先端までの全長でL2以上確保。
- 余長を8d以上とする。(90°折曲げの場合の余長は8d以上と覚える)
- 定着起点から鉄筋外面までの投影定着長さLaを確保する。
Laの数値は原則として柱せいの3/4以上とする。
小梁、スラブ上端筋(片持ちの小梁・スラブを除く)の場合はLbを確保する。
また梁の定着は上端筋と下端筋に適用されます。
長期荷重時には梁の上側が引張となりますが、地震時には地震力が左右からかかるため、梁の上下とも引張側になるケースがあるためです。
↑↑↑↑
こんな事が書いてありました。
昔は…以前は最低100アンカー以上とか10dなど仕様書に記載されていたと思ったのですが…うーん問題の答えはわかっていたとしても、参考書から勉強しないと正解に近い解説ができないですね。
自信過剰です。思い込みになってしまいます。
今後はもう少し調べててから解答していきたいと思います。
とりあえず、11問目の解答は✖️です。
屋根のスラブも一般階のスラブも特記がない場合は同じでL3の10d(鉄筋の太さの10倍)又は150㎜以上で、5dは間違えています。
私の実力もこんなものです。
今ならいきなり試験を受けても90…以下の不合格になるかもしれないです。
今後はみなさん私も含めてお互いに頑張りましょう。
仕事もブログも頑張ります。