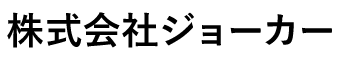みなさんこんにちはジョーカーの中村です。
今週月曜日になりました。
張り切って参りましょう。
以前に暖冬の話をしました気象変動で、さっそく早朝のニュースで全国各地で気象問題が起きています。
青森県ではホワイトアウト、全国各位で水位の減少です。私達も通勤経路で毎日大きな橋を渡っています。最近木曽川や揖斐川、長良川の水位が低く川底の石が見える所があります。今後もしかしたら水不足になるかもしれないですね。
温暖化に向けて心がけて省エネ、節水、アイドリングストップや渋滞を無くしたいですね。あとマイバックですか、ストローは本当に意味がわからないけど、紙は木の伐採でしょ!要するにプラスチックを海に流さなければいいだけだと思うけど、ストローが紙なのは賛否両論なので頭の良い人達にお任せしましょう
それではさっそく7問目に入ります。
日本建築学会 建築工事標準仕様書(JASS5)によれば、下図に示す鉄筋の加工後の全長
(ℓ)の許容差は、特記のない場合、±50mmとなっている
フリガナ
にほんけんちくがっかい けんちくこうじひょうじゅんしようしょ(JASS5)によれば、かずにしめすてっきんのかこうごのぜんちょう(ℓ)のきょようさは、とくきのないばあい、±50㎜となっている
まず日本建築学会 建築工事標準仕様書は日本の標準仕様書で鉄筋コンクリートの技術的な組み方、品質、材料、構法などのルールをJASS5と呼びます。
私はいつも安全、品質、コスト(料金)などを外国留学生に説明しています。ひとまとめにルールです。
施工に関しては5S=整理、整頓、清掃、清潔、躾を5つを使い、鉄筋の5Sは型枠大工の5Sは足場は解体はコンクリート打設の5Sはなど施工を五段階に分けて説明しています。ルールや5Sを使い急成長をしてくれる事を望んでいます。
何を言っているのこの人とか思われてしまうので、簡単に説明すると
5S活動とは「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「しつけ」の5つのSから始まる言葉の総称です。 5Sは製造業やサービス業でよく活用されています。 5S活動を行うと、職場環境が整うだけでなく、無駄もなくなります。 結果として、作業の効率化、生産性の向上が実現できます。
ググって貼り付けました。
この繰り返しの作業を使い説明しています。
この5Sは世界中で使われていると聞きましたので、異国の実習生に説明すると理解しやすいと思い私的にアレンジしました。
こんな私が自分で考えるくらいなので、たぶんどこかの学校で違う呼び名学んでいるかもしれないです。
盗んでいるつもりはないので正式名称とかありました教えてもらいたいです。
それでは、鉄筋施工に例えると
整理は準備です。
図面の不具合や鉄筋加工の拾い出し
元請けさんと打ち合わせと提案、施工変更、他業者さんの絡み、現場に行って下見や材料の置き場所やクレーンの配置、組み立ての期間と工期等、必要な道具や使用する材料等
いろんな事をイメージ作戦を練り、何度も何度も繰り返し自員人数をイメージします。
例えば、毎朝今日の一日に必要な道具を準備します。
次に整頓は配置です。
鉄筋の場合は、重いものや、施工するスペースしかない場合もある。配置方法や配筋方向、組立順序はとても必要不可欠です。
1番目の材料、2番目の材料と3.4…と荷揚げる順番を決めます。
私達は今橋梁壁高欄の打設足場を組んでいます。
100メートル以上の足場を1つ1つ資材を運んで組立てるよりも、少人数の場合運んでから組立てる方が効率良く仕事が進むと思います。

次に清掃は組立で例えて順番です。
どの職種にも同じですが、順番を間違えると無駄な時間のコストが掛かります。
順序が正しいと品質の良い鉄筋の配筋が組めたり安全な作業ができる事もあります。
施工をするみんなで作戦を練るのも、物作りの楽しみの1つです。
次に清潔は当然ながら片付けです。
これがしっかりしていないと、客先から評価されません。不要材料や組立資材、切断したゴミ、結束線等施工をすると多くのゴミが出てきます。鉄筋施工になると後でゴミが取れない事もあります。こまめな片付けは不可欠です。
最後に躾、検査です。
施工する段階から必要ですが、結束線のヒゲや玉
かぶり、ピッチ、ジョイントの長さ、太さ、本数等いろんなチェック項目があります。
これどこもやっていないと思いますがみんなでチェックするととても効率が良くて次回もっと品質の良い施工ができます。
いつのまにかうちの会社も経験だけは多いがチェックや片付けができない人が多くいます。
終業時間前に片付けと言うと、片付け=終わりと勘違いしています。片付けも重要な仕事なのにわかっていませんね。
自習生と日本人の差別という訳ではないですが、教育が出来て成長が早くすぐに追い抜いて行きます。
育てていくのが楽しいです。
いゃ〜また話がそれていきました。
とにかく世界共通の5Sを使い説明していくと成長が早いです。良かったらみなさんも使ってみてください。
次こそは問題の7問目を説明します。
最後に、JASS5も鉄筋のルールです。
JASS5の仕様書をよく見て、読んで理解して鉄筋の問題集を始めると尚更簡単に解ける問題があると思います。
それではまた次回よろしくお願いします。